2025.04.02
きょうだいで分担しての介護費用負担
2025.04.02
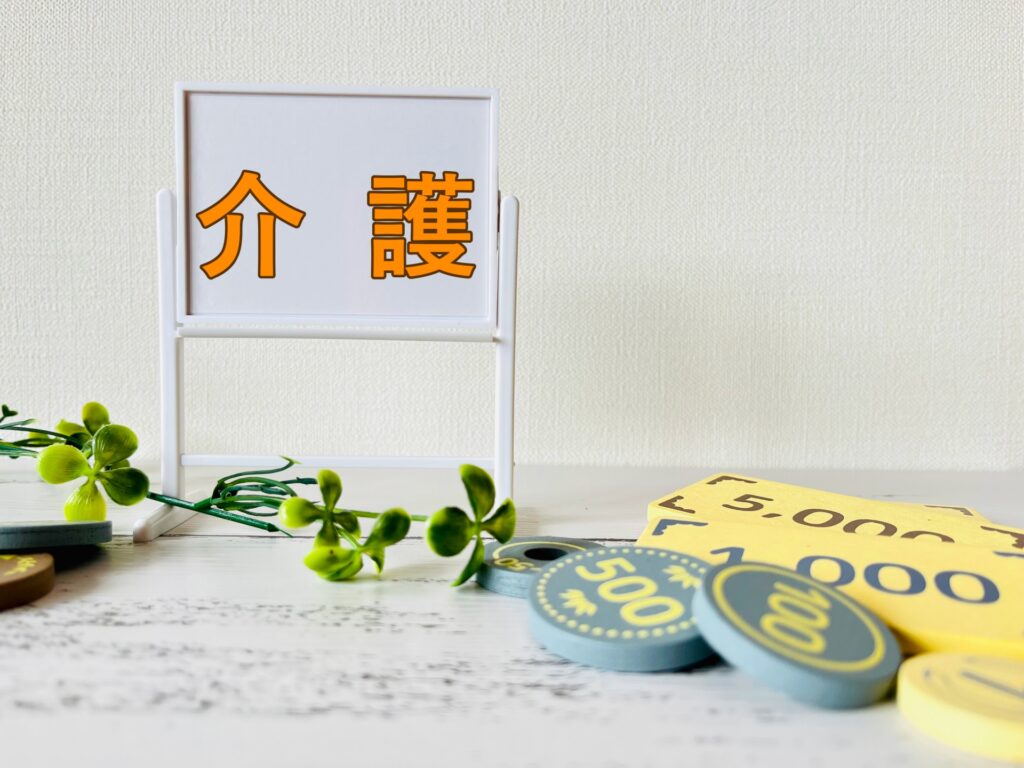
以前、「絶対にやってはいけない介護【前編】」で、
・その1:見守り・介護をきっかけとした同居
・その2:日常的に家族が直接介護に関わる
・その3;テレワークを活用した仕事と介護の両立
「絶対にやってはいけない介護【後編】」で、
・その4:育児同様に介護休暇・休業を利用して介護する
・その5:きょうだいで分担して介護費用負担
というコラムをお届けしました。
今回はその中でも、2025年4月の「育児・介護休業法」の改定を機に、「きょうだいで分担しての介護費用負担」の内容をさらに掘り下げてお伝えします。
●父を助けるためにきょうだいでの実家通い
Aさんの両親は自営業を営みながら、3人の子どもを大学まで通わせ、それぞれを独立させました。70代半ばで自営業を辞め、母親は地域のサークルに通い、父親は毎日の散歩と読書を楽しんでいました。時には夫婦で旅行に出かけ、老後の生活を満喫していました。
ただ、コロナ禍で母親が通っていたサークルが無くなり、父親は毎日の散歩を辞めてしまいました。家に閉じこり一気に老け込む両親をAさんは心配していました。
そんな両親のために、きょうだいが順番に実家に通うことになりました。母親に物忘れがみられ、心配する父親が常に近くにいなければ、と家の中で閉じこもっていたのです。母親任せだった家事を担う父親は、イライラから母親を叱責することもありました。Aさんは父親に、母親の病院受診や福祉窓口への相談を提案するも、父親は頑なに拒みます。仕方なく、Aさんきょうだいは実家を訪問する頻度を増やすことにしました。
●きょうだいで費用を分担して母親は高額な老人ホームへ
あるとき、次男の単身赴任が決まり、これ以上の両親のサポートできないので、母親の施設入所を父親に説得しよう、と相談がありました。
Aさんがいろいろ調べて、きょうだいで月10万円ずつ費用を分担する民間の老人ホームに母親が入所する資金計画を作り、弟や妻にも説明。みんなから了承を得ることができました。
Aさんが「お金は子どもたちで何とかするから、母さんを施設に預けよう」と懸命に説得をすると、その迫力に負けた父親は納得してくれました。母親は老人ホームで持ち前の社交性により友人を作りながら穏やかに過ごしていました。父親も母親と距離が取れたことで、毎日の散歩のついでに母親の面会に行き、読書の趣味も再開することができました。
●弟の妻が病気で費用負担が困難に
数年後、弟(三男)の妻が病気になり、母親の施設代月10万円の負担が難しい、と連絡がありました。
月30万円の施設代を3人で10万円ずつ負担してきましたが、それが払えないと施設を退去して、再び父に負担が掛かります。一方で、次男は子どもが生まれたばかりで、自身も息子が私立の高校に入学し、今以上に負担を増やせません。
きょうだいで話し合うも、互いを攻め合う口論に発展して、Aさんが「俺が家に引き取って面倒見る!」と感情的になり、三男とは音信不通になってしまいました。
●親の長生きが喜べる介護体制づくり
Aさんきょうだいは、実家で母親の直接的なサポートで疲弊し余裕を失い、自営業のため国民年金しかない両親が負担できない、すぐに入居できる民間の有料老人ホームを選ばざるを得ませんでした。
その選択をする前に、地域包括支援センターやケアマネジャーに、父の介護負担が過度となっている現状を相談し、母親にヘルパーやデイサービス、ショートスティを利用しながら、(公的な)特別養護老人ホームに入所すれば、両親の資産・収入で賄うことが十分可能でした。両親も自分たちの介護できょうだいが衝突することは望んでいないはずですし、子どもたちも親が長生きすることを喜べなくなってしまいます。
●きょうだいで介護費用を分担するリスク
介護の平均期間は4年7か月と言われていますが、親の介護が10年続いた場合、きょうだいそれぞれの家族に病気などで突発的に経済状況が急転する可能性も高くなることも考えられます。それぞれの負担が過度にならないために、親の資産や収入だけで介護費用を賄うことを考えてみてください。

